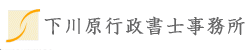日本で事業を経営・管理する外国の方がお持ちの在留資格「経営・管理」について、在留期間を更新し、引き続き日本での活動を続けるためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。ここでは、「経営・管理」の在留資格の在留期間更新に関連するポイントを解説いたします。
1.「経営・管理」の在留資格に係る活動の継続性
在留資格「経営・管理」は、事業の経営または管理を行う活動を行うためのものです。したがって、その活動を継続するためには、事業が継続的に運営されていることが求められます。単年度の決算状況だけでなく、貸借状況等も含めて総合的に判断されます。
特に、直近二期の決算状況に基づき、事業の継続性については以下のように取り扱われます。
- 直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
- 直近期末において欠損金がない場合
- 直近期に当期純利益があり、期末に剰余金がある場合は、事業の継続性に問題ありません。
- 直近期が当期純損失でも、売上総利益があり、剰余金が減少したのみで欠損金が生じない場合は、事業継続に重大な影響を及ぼすとは認められず、継続性があると認められます。
- したがって、直近期末において剰余金がある場合、または剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められます。
- 直近期末において欠損金がある場合
- 直近期末において債務超過となっていない場合:事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書や予想収益資料の提出が求められます。事業が行われていることに疑義がある場合を除き、原則として事業の継続性があると認められます。ただし、資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の第三者評価書の提出が更に求められる場合もあります。
- 直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合:債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなること)の見通しがあることを前提に事業の継続性が認められます。中小企業診断士や公認会計士等の第三者による改善見通し評価書の提出が求められ、これを参考として判断されます。
- 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合:債務超過が1年以上経過しても改善されない場合、原則として事業の継続性があるとは認められません。
- 【新興企業(設立5年以内の国内非上場企業)の特例】:独自性のある技術やサービス等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初の赤字は想定されるため、柔軟に判断されます。中小企業診断士等による改善見通し評価書、投資家等からの資金調達を示す書類、製品・サービスの開発等を示す書類の提出が求められます。
- 直近期末において欠損金がない場合
- 直近期及び直近期前期において売上総利益がない場合:原則として事業の継続性があるとは認められません。
- 【新興企業の特例】:上記同様、柔軟に判断されます。中小企業診断士等による改善見通し評価書、資金調達を示す書類(十分な手元流動性がある場合を含む)、開発等を示す書類の提出が求められます。
主な用語の説明
- 直近期:直近の決算が確定している期。
- 直近期前期:直近期の一期前の期。
- 売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額。
- 剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金。
- 欠損金:期末未処理損失、繰越損失。
- 債務超過:負債が資産を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が「資産の部」の合計を上回った状態)。
2.事業所に関する要件
「経営・管理」の在留資格に係る活動を行うためには、事業所を有していることが必要です。
- 事業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約において使用目的が事業用(事業、店舗、事務所等)であることを明確にし、契約者名義も当該法人等の名義とする必要があります。
- 月単位の短期間賃貸スペースや容易に処分可能な屋台等は、事業所として認められません。
- 設立当初のベンチャー企業などで、住居としても使用している施設を事業所とする場合、貸主が住居目的以外での使用を認めていること(事業所として当該法人が転貸借することにつき、貸主が同意していること)、および借主も当該法人が事業所として使用することを明らかにしていることが必要です。
3.事業者としての義務の履行
在留資格「経営・管理」で在留する外国人は、自らの運営する機関が、法令に基づく義務を履行することが求められます。
4.その他の一般的な在留期間更新要件
「経営・管理」の在留資格に限らず、すべての在留資格の更新許可申請に共通する一般的な要件もあります。
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと:正当な理由なく、現在の在留資格で認められている活動を行っていない場合は、更新において消極的な要素として評価されます。
- 素行が不良でないこと:素行が善良であることが前提です。退去強制事由に準ずる刑事処分や、不法就労のあっせんなど、出入国在留管理行政上看過できない行為を行った場合は、素行が不良と判断されます。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること:日常生活において公共の負担となっておらず、将来安定した生活が見込めること(世帯単位で判断されます)が求められます。ただし、人道上の理由がある場合は考慮されます。
- なお、年齢や扶養状況など、日本入国後に事情が変わった場合でも、そのことだけで直ちに在留期間更新が不許可となるわけではありません。
これらの要件を満たしているかが、在留期間更新許可申請において審査されます。
ご自身の状況がこれらの要件に適合しているかご確認いただき、必要な書類を準備して申請に臨むことが重要です。ご不明な点等ございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。