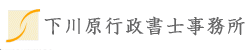「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を配偶者として申請する際、「質問書」の提出は必須となります。この書類は、申請内容の審査において極めて重要な参考資料となります。
本記事では実際の質問書の様式に基づき、各項目の記載要領と作成上の留意点について、専門的な観点から解説いたします。
「質問書」提出の意義と重要性
質問書は、申請者である外国人の方と配偶者の方との婚姻が真実であり、かつ、日本において安定・継続した婚姻生活を営む意思と実態があることを入国管理局に対して具体的に明らかにするための書類です。
残念ながら、在留資格の不正取得を目的とした偽装結婚も散見されるため、出入国在留管理局は提出された各種資料に基づき、婚姻の信憑性について慎重な審査を行います。質問書は、申請書本体だけでは網羅できない、お二人の交際経緯や意思疎通の状況、双方の家族の関与といった詳細な情報を提供し、審査官が実態を把握するための重要な資料となります。
虚偽の記載は、審査上著しく不利な結果を招くだけでなく、場合によっては法的な責任を問われる可能性もあります。 提出前には記載内容に誤りがないか細心の注意を払い、必ずご自身で署名することが求められます。
主な質問項目と記載上の留意点
以下に、一般的な質問書の項目と、それぞれの記載における留意点を解説します。
1. お互いの身分事項について
- 申請人(外国人の方)及び配偶者(日本人または永住者の方)の氏名、国籍、生年月日、現住所、電話番号、職業、勤務先の名称・所在地・電話番号、就職年月日などを正確に記入します。
- 住居に関する情報(自己所有または借家、家賃、間取り等)も記載が必要です。
- 留意点: パスポート、在留カード、住民票、運転免許証、登記事項証明書、賃貸借契約書等の公的書類や正確な情報源に基づき、一字一句違わずに記載してください。
2. 結婚に至った経緯(いきさつ)について
この項目は、婚姻の信憑性を立証する上で最も重要な部分であり、極めて詳細かつ具体的な記述が求められます。
- (1)① 初めて会った時期・場所:
- 年月日及び具体的な場所を正確に記載します。
- ② 初めて会ってから結婚届を提出するまでのいきさつ:
- 時系列に沿った詳細な説明: 出会いの状況から交際の開始、関係の進展、プロポーズ、双方の親族への紹介・挨拶、結婚の合意、そして婚姻届の提出に至るまでの過程を、具体的な年月日を示しながら、詳細に記述します。
- 客観的な事実の記載: 交際中の連絡手段(電話、メール、SNS等)の頻度や内容、デートの場所や頻度、金銭的な援助の有無など、具体的な事実を客観的に記述することが重要です。
- 補足資料の活用: 説明に関連する写真(二人で写っているもの、双方の家族と一緒のもの等)、手紙、メールの記録、国際電話の通話明細、SNSのスクリーンショットなどを任意で添付することが可能です。 これらは交際の信憑性を高める上で有効な資料となり得ます。
- 別紙の使用: 記述スペースが不足する場合は、別紙に適宜内容を追記し、添付することができます。
- (2) 紹介者の有無などについて:
- 結婚相談所や知人等からの紹介により知り合った場合は、「有」にチェックを入れ、紹介者の氏名(結婚相談所の場合は会社名)、国籍、生年月日、住所、電話番号、申請人及び配偶者との具体的な関係性(単に「友人」ではなく、いつからの友人でどのような関係か等)を詳細に記載します。 紹介年月日、場所、方法(対面、E-mail等)も正確に記述します。
3. 夫婦間の会話で使われている言語について
夫婦間の円滑な意思疎通が可能であるかを示す項目です。
- (1) 日常会話で使用する言語: 具体的な言語名を記載します(例:日本語、英語)。
- (2) お互いの母語(国語): それぞれの母語を記載します。
- (3)(4) 相手の母語の理解度: 選択肢(「難しい=通訳が必要」「筆談/あいさつ程度」「日常会話程度は可能」「会話に支障なし」)から、現状に最も近いものを選択します。
- (5) 申請人の日本語学習歴: 申請者(外国人の方)が日本語を理解できる場合、いつ、どこで、どのような方法で日本語を学習したのかを具体的に記述します。
- (6) 言葉が通じない場合の意思疎通方法: 翻訳アプリの使用、筆談、ジェスチャー、あるいは通訳者の介在など、具体的なコミュニケーション手段を説明します。 通訳者がいる場合は、その氏名、国籍、住所を記載する欄があります。
4. 日本国内で結婚された方は、結婚届出時の証人2名を記入
- 日本国内の市区町村役場へ婚姻届を提出した際に、届出書に署名した証人2名の氏名、住所、電話番号を正確に記載します。
5. 結婚式(披露宴)を行った方は、その年月日と場所等を記入
- 挙式や披露宴を実施した場合、その年月日、場所(名称、所在地)、申請人側・配偶者側それぞれの主な出席者(父母兄弟姉妹、子など)及び双方の合計出席者数を記載します。
6. 結婚歴について
- 申請人、配偶者それぞれについて、初婚または再婚の別を明記します。
- 再婚の場合は、何回目の婚姻であるか、前回の婚姻期間(年月日~年月日)、及びその婚姻の解消原因(離婚または死別)を正確に記載します。
7. 申請人(外国人の方)の過去の来日歴
- 過去における日本への渡航歴について、回数、それぞれの渡航期間(年月日~年月日)、及びその際の主な来日目的(例:観光、親族訪問、短期商用、留学など)を記載します。 多数にわたる場合は、直近のものを優先して記載するよう指示があります。
8. 配偶者(日本人または永住者の方)の申請人母国への渡航歴
- (1) 知り合ってから結婚までの間 及び (2) 結婚後 に分けて、配偶者が申請人の母国を訪問した回数と、それぞれの渡航期間(年月日~年月日)を記載します。 こちらも多数の場合は直近のものを記載します。
9. 申請人の退去強制歴・出国命令歴の有無
- 過去に日本から退去強制処分または出国命令を受けたことがあるか否かについて、正直に「無」または「有」にチェックを入れます。 「有」の場合は、その回数も記入します。
10. 9で「退去強制されたことがある」と記入された方への質問
- (1) 違反の内容: 不法残留、不法入国、その他(具体的に記述)から該当するものを選択します。
- (2) 退去強制等により出国した年月日(直近のもの)及び出国した空港名。
- (3) 当時使用していた旅券の国籍、氏名、生年月日が、今回の申請におけるものと同一か否か。異なる場合は、当時の情報を記載します。
- (4) 退去強制されるまでの間に夫婦で同居した事実がある場合は、その期間と住所を記載します。
11. 申請人及び配偶者の親族について
- (1) 父・母・兄弟姉妹について: 申請人側、配偶者側双方の親族(父、母、兄弟姉妹)について、続柄、氏名、年齢、住所(海外居住の場合は都市名まででも可)、電話番号(日本に居住している場合は可能な限り)を記載します。 父母が亡くなっている場合は、住所欄に「死亡」と記載します。
- (2) お子さんについて: 実子及び養子がいる場合は、続柄、氏名、生年月日、住所を記載します。 いない場合は「なし」と記載します。
12. 親族で今回のご結婚を知っている方はどなたですか
- 夫側、妻側それぞれで、今回の結婚の事実を了知している親族(父、母、兄弟姉妹、子)を○で囲みます。
最終確認と署名
- 全ての項目への記入が完了したら、記載内容に誤りや遺漏がないかを再度確認し、配偶者(通常は日本人または永住者の方)が自署し、作成年月日を記入します。
質問書作成における重要な留意事項
- 正確性・具体性の担保: 全ての記載は事実に即し、曖昧な表現を避け、可能な限り具体的に記述してください。
- 夫婦間の情報共有と整合性: 作成にあたっては夫婦間で十分に情報を共有し、記憶を相互に確認することで、矛盾のない内容とすることが肝要です。
- 他の提出資料との整合性: 申請書本体や添付する証明書類、スナップ写真の説明など、他の提出資料との間で内容に齟齬が生じないよう注意が必要です。
- 誠実な対応: 空欄は極力避け、該当事項がない場合でも「該当なし」「特になし」等と明記することが望ましいです。
専門家(行政書士)への相談
質問書の作成は、配偶者ビザ申請手続きにおいて非常に重要なプロセスであり、その内容が審査結果に大きく影響を及ぼす可能性があります。記載内容に不安がある場合、または手続き全般に関して専門的な助言や支援が必要な場合は、経験豊富な行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
行政書士は、個別の状況を詳細にヒアリングした上で、出入国在留管理局に対し婚姻の信憑性や安定性・継続性を効果的に訴求できるような質問書の作成を支援し、その他の必要書類の収集・作成から申請取次まで、手続きを総合的にサポートすることが可能です。