2024年6月より開始された監理措置制度について、入管庁の資料に基づいてまとめてみます。
監理措置制度は、退去強制手続において、収容することなく、監理人の監理の下、被監理者の逃亡などを防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら手続を進めるための収容代替措置として創設されました。この制度は、法律上「監理人による監理に付する措置」と定義されており、この措置に付された人を「被監理者」と呼びます。
退去強制手続の概要
退去強制とは、国家が好ましくないと認める外国人を領土主権に基づき、行政手続により、その領域外に退去させることとされています。退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由がある外国人に対して、退去強制手続が開始されます。
退去強制手続の流れの一例として、関係機関からの通報や摘発により、入国警備官による違反調査が行われます。その後、主任審査官による審査を経て、退去強制事由に該当することが認定された場合、特別審理官による判定、法務大臣による裁決という段階を経て、退去強制令書が発付されます。在留資格のない者は、退去強制手続又は出国命令手続を経なければ出国できません。
監理措置の種類と要件
監理措置には、退去強制令書発付前のもの(入管法第44条の2以下に規定)と、退去強制令書発付後のもの(入管法第52条の2以下に規定)があります。
主任審査官が、退去強制手続を行うにあたり、対象となる外国人を収容しないことが相当と認められる場合に、監理措置決定を行います。監理措置決定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 監理人が選定できること。
- 主任審査官が、対象となる外国人が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること(退去強制令書発付前)。
- 主任審査官が、対象となる外国人が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること(退去強制令書発付後)。
被監理者の遵守事項
被監理者は、次の事項を遵守する必要があります。
- 監理措置決定通知書の携帯・提示義務:在留カードを持っている場合を除き、常に携帯し、入管審査官、入国警備官、警察官、地方公共団体の職員等に要求されたときは提示しなければなりません。監理措置決定通知書には、退去強制令書発付前後のいずれの規定による監理措置か記載されています。
- 監理措置条件の遵守:監理措置決定通知書に記載される条件を守る必要があります。主な監理措置条件は以下の通りです。
- 住居
- 行動範囲の制限(原則として、指定住居の属する都道府県の区域内)
- 呼出しに対する出頭の義務(届出義務とは異なります)
- その他逃亡等を防止するために必要と認められる条件(例:逃亡及び証拠の隠滅の禁止(発付前)、逃亡及び就労の禁止(発付後))
- 上記のほか、主任審査官が必要と認めるときは、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされることがあります。
- なお、監理措置条件に違反した場合には、監理措置決定が取り消されることがあります。
- .定期的な届出義務の履行:主任審査官が指定する日から3月を超えない範囲内で、地方出入国在留管理官署に出頭し、監理措置条件の遵守状況や監理人との連絡状況などを届け出なければなりません。郵送による届出は認められていません。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、監理措置決定が取り消されることがあります。
報酬を受ける活動の許可
在留資格がない外国人は、原則として就労できません。しかし、退去強制令書が発付される前の被監理者に限り、例外的に報酬を受ける活動に従事することが許可されることがあります。退去強制令書発付後の被監理者は、報酬を受ける活動はできません。
退去強制令書発付後の被監理者に就労が認められない理由として、我が国において活動する外国人は、適法に在留資格を取得し、それに従った活動を行うのが原則であり、退去が確定した者に就労を認めることは在留資格制度の根幹を損なうと考えられること、また、就労を無制限に許可すると就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という法改正の趣旨を没却することとなりかねないことなどが挙げられています。
報酬を受ける活動の許可は、以下のいずれの要件にも適合すると認められる場合に許可されることがあります。
- 退去強制令書発付前の被監理者からの申請であること。
- 当該申請を行うことについて監理人の同意があること。
- 従事しようとする活動が、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当なものであること。
- 当該活動に従事することが、被監理者の生計を維持するために必要であって、その報酬額が生計の維持に必要な範囲内であること。なお、生計の維持に必要な範囲内の報酬額の上限は、生活保護の水準などを参考に個別に判断されるとのことです。
- 当該活動に従事することが相当と認められること。
- 当該活動が監理人による監理の下で行われるものであること。
許可された場合には、監理措置決定通知書に勤務先、活動内容、報酬額の上限などの条件が記載されます。
許可されない活動の例としては、法令に違反する活動、風俗営業等や性風俗特殊営業等に関連する活動、源泉徴収義務を適切に履行していないと認められる機関での活動などがあります。また、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動」が対象であるため、被監理者が自ら会社を経営するなど、収入を伴う事業を運営する活動を行うことは許可の対象外とのことです。
退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けずに報酬を受ける活動又は収入を伴う事業を運営する活動を行った場合、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨規定されています。退去強制令書発付後の被監理者がこれらの活動を行った場合も同様です。
被監理者に退去強制令書が発付されているか否かは、交付された監理措置決定通知書を確認することで確認できます。発付前の監理措置は入管法第44条の2、発付後は第52条の2の規定によるものと記載されており、また、就労が認められない退去強制令書発付後の通知書には「就労の禁止」が条件として記載されています。
監理人
監理人は、以下の3つの要件を満たしている者から選定されます。
- 監理人の責務を理解していること。
- 監理措置決定を受けようとする外国人の監理人となることを承諾していること。承諾する場合は、監理人承諾書兼誓約書を提出します。
- 任務遂行の能力を考慮して、監理人として適当と認められること。任務遂行能力は、年齢、職業、収入、資産、素行、外国人の関係、金銭支払いの相当性などを総合的に勘案して判断されます。未成年者、精神機能の障害がある者、在留資格を有していない外国人などは、任務遂行能力が認められない例として挙げられています。
監理人は、典型的には被監理者の親族や知人など身近な人が想定されていますが、これに限らず、行政書士、弁護士、支援者、登録支援機関の職員などもなり得ます。
監理人の責務は、以下の4つです。
- 被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと:例えば、定期的に連絡を取り、監理措置条件や届出義務を守っているか確認し、条件などを守って生活できるよう必要な指導・監督を行います。ただし、常時、本人の生活状況を把握するなどの過度な負担を求めるものではないとのことです。
- 被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を行うよう努めること:例えば、被監理者が入管へ届出に行く際に付き添ったり、入管の手続きについて相談を受けた際に担当窓口を教示したりします。
- 届け出るべき事由(届出事由)が発生した場合には、届出を行うこと:被監理者が監理措置決定の特定の取消事由に該当したことを知ったとき、被監理者が死亡したとき、監理人や被監理者に関する変更事項(氏名、電話番号、親族関係・雇用関係の終了など)があったときなどが届出事由となります。監理人は、これらの事由が発生したことを知ったときから7日以内に届け出なければなりません。他方で、定期的な届出は必要ありません。なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、監理人の選定を取り消されたり、処罰を受けることがあります。
- 主任審査官から報告を求められたときは、報告をすること:主任審査官は、被監理者の生活状況や監理措置条件の遵守状況などを確認するため、監理人に対し報告を求めることがあります。例えば、被監理者からの届出内容の信憑性を吟味するためや、逃亡・不法就労活動の疑いがある場合などです。報告要求書が交付されたときは、報告の期限までに報告しなければなりません。報告を求められたときに報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときは、監理人の選定を取り消されたり、処罰を受けることがあります。
監理措置決定の取消し
監理措置決定は、以下の事由に該当する場合には取り消すことができる、又は取り消さなければならないとされています。
- 取り消すことができる事由
- 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
- 証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき(発付前)。
- 監理措置条件に違反したとき。
- 報酬を受ける活動の許可を受けずに活動を行ったときなど(発付前)。
- 退去強制令書発付後の被監理者が収入を伴う事業運営活動や報酬を受ける活動を行ったときなど(発付後)。
- 届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき(発付後)。
- 取り消さなければならない事由
- 保証金を納付することが条件とされた場合に、保証金を納付しなかったとき。
- 監理人の選定が取り消された場合等において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
監理措置決定が取り消されたときは、監理人に対して取消等通知書が交付され、通知されます。監理人は、自己が監理する被監理者の監理措置決定が取り消されたこと自体をもって処罰されることはありません。ただし、被監理者が取消事由のいずれかに該当することを知ったにもかかわらず、届出義務を履行しなかった場合などは処罰を受けることがあるとのことです。
監理人の選定取消しと辞任
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときや、任務を継続させることが相当でない(例えば、届出・報告義務に違反したとき)と認められる場合には、監理人の選定を取り消すことができます。
監理人を辞任する場合は、あらかじめ主任審査官に届け出る必要があります。辞任しようとする日の30日前までに、辞任理由や年月日などを地方出入国在留管理官署に届け出るよう努めるものとされています。
監理人が責務を果たさなかった場合には、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断され、監理人の選定が取り消されることがあります。また、特定の届出・報告義務違反に該当する者は、10万円以下の過料(行政罰)に処されると規定されています。
各種申請
監理措置制度に関連して、以下の申請を行うことができます。
- 監理措置決定申請:監理措置決定申請書、監理人承諾書兼誓約書、監理人になろうとする者の身分証明資料、申請者の収入・資産疎明文書、住居資料、申請理由疎明資料などを提出します。
- 報酬を受ける活動の許可申請:報酬を受ける活動の許可申請書、労働条件明示文書、就業予定機関に関する資料、申請者や生計を一にする親族等の収入・資産疎明資料、監理人等からの援助に関する資料などを提出します。
- 行動範囲拡大許可申請:監理人と連名による申請書のほか、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間などを疎明する添付資料を提出します。
- 指定住居変更申請:監理人と連名による申請書のほか、変更後の住居や住居変更の必要性を疎明する添付資料を提出します。
監理措置に関して分からないことがある場合は、出入国在留管理庁のウェブサイトを確認するか、地方出入国管理官署または当事務所にお問い合わせください。
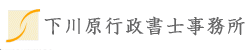



コメント